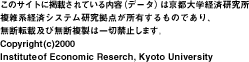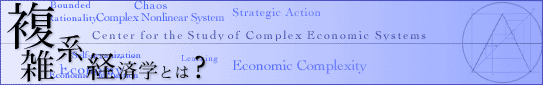 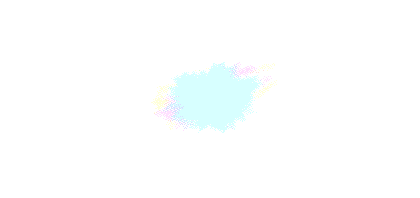 |
|
| これまでの科学では、一つの現象を研究するにあたって、対象をできるだけ小さ
な単位に分割してゆき、その原因を見つけるという方法をとってきた.これを還元 主義的方法と呼ぶ.経済学ではミクロ経済学がこれにあたる.ところ が、個々の要素
を積み上げていっても、全体の動きを説明することはできない.複雑適応系は,従来 のマクロ的方法に代えて、個々の要素と、その相互の関係、すなわちネットワークに
よって全体の動きを説明する.還元主義的方法に対する、全包括的方法とでもいうべ きものである.複雑適応系が解明するもの、それもこれまでの還元主義的な方法で説
明できなかったことは、創発、進化、自己組織化などのキーワードで表現される現象 である.それらは,経済でいえば、企業の発生、変革、地域経済の発生な
どのことであるが、そのそれぞれが切り離して論じることのできない概念でもある.要素が互い に干渉しあうネットワークである複雑系は、必然的に動学、それも壮大な動学システ
ムとなる.国際地域経済の盛衰などは、経済史の対象とされてはいても、経済理論の 対象となる問題ではなかった.それを数理モデルで解析的にあるいはコンピュータ
ー でのシミュレーションで分析しようというのである. 1980年代の初めから、収穫逓増の生産関数と共にカオスなどの非線形動学分析が 経済学でも、盛んに行われてきた.また、1990年代に入って、これまでのマクロモデ ルに情報の不完全性や外部性を加味した新しい成長理論では、 外部性から生じる収穫 逓増が主に研究されている.更に、エージェント間の戦略的行動を加味することも可 能である.このようにして、経済動学は、市場を通じる相互依存、外部性を通 じての相互依存、戦略的行動を通じての相互依存と、エージェントを繋ぐいくつものネット ワークを もつのである.このネットワークの分析が,これまでの非線形均衡動学や新 しい成長理論をより一般化する複雑適応系としての経済分析なのである. エージェントの間の幾重にも重なるネットワークは、経済、生物、自然界に共通 に見いだされる.それゆえに、複雑系は異なる分野の研究者が共同で働く場を提供してくれる.複 雑系経済システム研究拠点でも学際的研究として,交渉の帰結についてのゲームの実 験、地球温暖化と経済理論、限定合理性の観点から人間の思考と行動についての脳磁 計を使った実験なども行っている. |